最近、ビジネス心理学を勉強し始めたので、それを備忘録としてアウトプットしていきたいと思います。
ビジネス心理をこれから勉強しようとしている人、もしくはすでに勉強中の人に対してなるべくわかりやすく解説していきたいと思います。
別にビジネス心理検定を受けない人でも、自分の職場で使える知識を記載するので、どうぞ読んでってください。
目次
職場で状況的学習を考えないといつまでも自分のせいにされる
みなさん状況的学習という言葉をご存知でしょうか?
これは、人の成長は状況に依存しているという心理学です。
状況とは主に4つ存在していると言われています。
会社で言うところPCやデスクや椅子などの会社の道具、上司や部下などの人、社内規範やマニュアルなどのルール、仕事の成果やどこに向かって行動するかなどの結果です。
多くの人は一般能力説に従って仕事をしている傾向にあります。
一般能力説とは人の能力は状況ではなく、その人の素質によるものであるという思い込みです。
つまり、優秀な人はどこに転職しても優秀であると思っているのです。
でも違いますね。よくよく考えてみると人の成長は本人の能力だけで決まるわけがありません。
その状況によって人の成長スピードは違うということを上司や部下は認識しないといけないいうのがビジネス心理の考え方です。
なので、よく人のミスはその人本人によるものであると帰属されることがあります。
学習的状況という立場から考えると組織のあり方に問題があるという視点で改善を見出していくのです。
つまりミスの原因はその本人によるものだけではなく、ミスしやすい状況を作り出している組織にあるということになります。
応用の仕方を教えるのが大事、学習の移転を考える
優秀の人はどこへ行っても優秀とは限らないことを先ほどお伝えしました。
まず、この考え方を捨てましょう。
一般能力説を払拭することができたなら、自然と学習の移転を考えて教育できます。
学習の移転とは「ある場面で習得した知識やスキルを別の場面で使いこなすこと」です。
ここで以下に学習の移転を企業研修で適用させたカーステン・オスターランドの有名な事例を見てみましょう。
研修と現場のギャップをなくす学習の移転を考えた企業研修
とある企業で営業研修を行いましたが、その研修ではある問題が起きていました。
それは研修で学んだことを現場で活かせないという状況が起きていたのです。
この問題の対象となるのは、何を目的としていたかです。
今回の営業研修では講師の満足度を高めることが目的になっていました。
この研修で学んだことを現場で活かすには研修と現場の乖離をなくしていくような研修が必要だったのです。
そこでカーステン・オスターランドは学習移転の理論に従って、研修と現場のギャップをなく必要があることを課題として設定しました。
そしてその課題を克服するにあたって、ある二つの視点で改善案を導き出しました。
一つは移転モデルという考え方に従った組織改善案です。
どういうものかというと、知識のギャップをなくすことに重点を置いて研修カリキュラムを組み直したのです。
もう一つは越境モデル。
こちらはどういうものかというと、組織内での壁を超えることに重点を置いた考えです。
部署を越え、上司や部下など関係なく意見交換し、職場全体で現場との乖離を克服するように全体で取り組んでいくという考え方に従った組織改善案です。
そして、この移転モデルと越境モデルによって研修での学びを現場でより早く活かせるように改善していったといいます。
対話は大事。越境的対話で組織全体を活性化する
社員の職場での学びを加速させるには、この越境を考えていくことがビジネス心理では重要になってきます。
「越境」というのは文字通り境を超えるという意味です。
もう一つここで大事になってくるのが社内で社員同士がどれだけ対話しているかです。
なので、部署や上司部下関係なく組織改善のための話し合いの場をもうける越境的対話というのが必要不可欠です。
越境的対話では組織のあり方を批判的に反省し、組織のものたちが自らの手で協働的にそれを改善させていくのです。
よくあるのが、上司と部下の対話不足によって人的ミスが引き起こされます。しまいには労災としてのうつ病や自殺にもなりかねません。
その原因はある特定の社員が十分二コミュニケーションをとれていないことによる、ある種の疎外感や孤独感からくるものでしょう。
根本を辿れば越境的対話が社内に浸透していないからと言い換えることができます。
だから、上司と部下との定期的な面談は大切で、社員のヘルスケアにもつながっていくのです。
雑談は以外と重要。無駄が仕事成長につながる?!
状況的学習では正統的周辺参加という考え方があります。
正統的周辺参加とは人の成長はその人の能力ではなく、様々なモノやルールの関わりを経て、その組織らしい成員として成長していくという考えです。
その考え方だと仕事での学びは二つの機会によって人は成長していく過程を辿ります。
一つは公式的共同体というものです。
公式的共同体とは周りが期待している仕事そのものです。
上司の頼まれた仕事に仕事に対し、進捗を報告したり、タスクが終わったら完了報告をするというような直接仕事に関わる部分になります。
もう一つの学びの機会は非公式的共同体と呼ばれるものです。
非公式的共同体とは休憩中のタバコ休憩、仕事中のちょっとした雑談などです。
直接仕事には関係のない仕事中に起こるいわゆる「無駄」に見えるものです。
多くの企業は公式的共同体に重点を置いて社員教育しています。
ですが、忘れてはならないのが非公式共同体の存在です。
一見タバコ休憩中の雑談や社員同士でのお昼休憩などは、仕事の成果とは関係ないように見えます。
ですがこう考えなければいけません。
例えば、新卒の研修で3ヶ月間の研修で一緒に過ごしてきた同僚たちがいたとします。
その研修での3ヶ月間では、お互いがそれなりにご飯にいったり、休憩で雑談を交わしたりして人間関係を深めていきました。
そして3ヶ月後、研修が終わり、お互い別々の部署へ配属されてしまいました。
しかし、配属先は研修の仲間が一人もいない。
すると、その部署ではゼロから人間関係を作らなければならず、職場に馴染むのに時間がかかり、その新人が活躍し始めるのに時間がかかる可能性があります。
まず仕事をするには職場に馴染まないことにはタスクがはかどりません。
そこで仕事には直接必要はないけれど、職場においては人間関係を深めることが、仕事のしやすさや昇級昇進への近道であることがしばしばあります。
その意味で非公式的共同体が活発的でない職場は、無機質で働く意欲がわきにくい状況がおきます。
そんな職場では新人が成長する期待はできませんね。








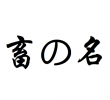



Very good information. Lucky me I discovered your
site by accident (stumbleupon). I’ve saved as a favorite for later!
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
reading your blog and I look forward to your new updates.
Excellent goods from you, man. I’ve be mindful your stuff prior
to and you’re simply extremely wonderful. I actually like what
you’ve acquired here, certainly like what you’re
stating and the way in which through which
you assert it. You make it enjoyable and you still take care of
to stay it smart. I can’t wait to read much more from you.
This is really a terrific web site.
Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty
finding one? Thanks a lot!
naturally like your website however you have to
take a look at the spelling on several of your posts.
A number of them are rife with spelling issues and I to find it very
bothersome to inform the truth however I will certainly come
back again.
It’s hard to come by knowledgeable people for this subject, however, you
sound like you know what you’re talking about! Thanks
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting
videos to your blog when you could be giving us something
informative to read?