陸上競技選手の方々。皆さんは100、200mなどの短距離種目において、どういう風なスタートを心がけていますか?
多くの陸上初心者や素人さんが速く走るためにスタートダッシュを究めようとしている中で、間違った意識によって練習している人をよく見かけます。
短距離を走る際において、スタートダッシュはとても重要です。
それではこれから、スタートダッシュを速くするためのポイントを解説します。
やさしく走ることがポイント
始めにご自身が陸上競技の短距離において、間違ったスタートダッシュをしているかどうかをチェックしましょう。まず走りを改善するには自分の今の走りの状態を知るべきです。
あなたの走りについて、こんな覚えはありませんか?
スタートダッシュ時に、バタバタと音を立てて走ってしまう。
どうでしょうか?実は上のこれらの特徴はスタートダッシュにおいてはすごく非効率な走り方です。
この事実が非効率な走りであることを分かりやすく説明した人物がいます。武井壮さんです。
ボーリングの球をイメージしてみてください。
ボーリングの球って結構重いですよね?まずあれを強く叩くイメージをしてみてください。
ボーリングの球を強く叩いてもとあまり前に進みませんよね?
それどころか痛いし、しかも大きな音を立てるだけで何も起きないと思います。
これは衝撃が球に吸収されてしまって前に進むという働きになっていないんです。
ところが、ボーリングの球を手でゆっくりと押すとどうなるでしょうか?
少ない力でスムーズに動かすことができます。
スタートダッシュの極意は実はここがポイントです。
話を戻すと、「スタートダッシュ時のバタバタと音を立てて走ってしまう」という走り方は、さっきのボーリングの球を強く叩く原理と同じです。
ただ大きな音を立てているだけで、ほとんど前に進む力に使えていないんです。
それどころか、バタバタと音が鳴ることで衝撃が自分自身の身体に来てしまっているので、怪我のもとです。
なので正しいスタートダッシュを目指すなら、
「なるべく音を立てない走り方を心がけるべき」
走りには技術が必要
音を立てずに走れるというのは、余計な体力を使わずに前方に大きな推進力を得ることにもつながります。
この効率的なスタートダッシュは後半の走りにも表れてくるものです。
例えば100mを走るときのことを考えてください。人は100mという短距離を走るには最初から最後まで本気で走ることはできないものです。
体の仕組み上無理なんです。
人が本気で筋肉を動かせる時間が最長7秒だといわれているからです。
それ故に効率的な走りを目指さなくてはなりません。
なので100mという人間にとって長すぎる短距離では、速く走るためには「技術」が必要になってきます。
前半に余計な筋肉を使わずに効率的にスタートダッシュを行えたなら、後半の走りに対しては、温存された力を使うこともできます。
なので100mでも200mでもそうですが、長距離だけじゃなくても短距離においてもペース配分に似た意識を持たせることが速く走るコツではないかと10年間陸上競技をやって分かったことです。
それは、なにも前半に本気を出さないというわけではありません。
より速く前に進むための本当に必要な筋肉や、体の使い方をするべきなのです。
先ほども説明したバタバタと大きな音を立てて走ることは、すでに後半に使えるはずだったエネルギーを無駄に使ってしまっているからなのです。
では、今あなたがバタバタしたスタートダッシュをしているのなら今すぐ改善するべきでしょう。でないと速く走れることからますます遠のいていきます。
まとめ
正しいスタートダッシュとは「ボーリングの球を手でゆっくり押す」ようなやさしい地面の着地をしながら走ることが大事。
そして、後半の走りも効率的に加速ができる。
>>次のページは
『ウサインボルト選手が指導したシンプルなスプリントドリルを動画付きで説明』

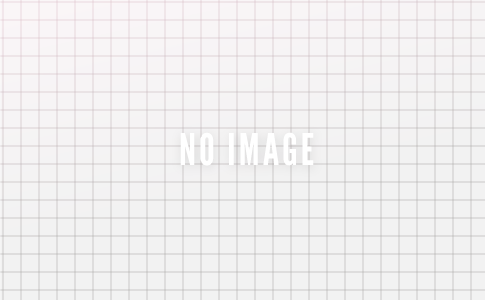




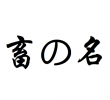






obviously like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts.
Several of them are rife with spelling issues and I
to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I’ll definitely come back again.
I like what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage!
Keep up the very good works guys I’ve included you guys to my own blogroll.
I every time emailed this weblog post page to all my associates, for
the reason that if like to read it then my links will
too.
To safeguard family members from deterioration?
Do you experience feeling who they may well be more freeze within your
home?
To maintain your belongings in complete safety?
Do you need dropping balcony panel in your property area?
I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
Maybe you could space it out better?
I must thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well.
In fact, your creative writing abilities has
inspired me to get my own, personal website now 😉
Thanks very nice blog!